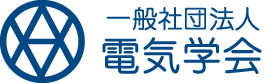標準化活動の識者に問う!どうすればいい日本の標準化活動! 座談会 実施報告
◇ 開催日時:2025年3月19日(水) 9時~12時◇ 場 所 :明治大学 中野キャンパス 5Fホール(※ご所属などは開催日のものです)
– – – 目 次 – – –
概要
テーマ1:標準化活動のプレゼンス
テーマ2:国際標準化における日本のイニシャチブ
テーマ3:分野横断への取り組み
テーマ4:オープン&クローズ戦略
テーマ5:人材育成・後継者育成
– – – – – – – – –
概要
令和7年電気学会全国大会にて標準化活動の重要性と,標準化活動が抱えている問題点について,広く認知してもらうことを目的にシンポジウムを開催しました。企業やアカデミアで標準化活動の活性化や人材育成を進めるに当たり,問題点や解決策を産官学の有識者にお集まりいただき,それぞれの立場から議論いただいた内容となっています。なお,本内容については,2023年4月に開催した「国際標準化活動に関する有識者座談会」(電気学会誌2023年8月号掲載)で出されたご意見を踏まえた内容となっており,ご興味がありましたら合わせてお読みいただくことで,一層,理解を深めることができます。
出席者(敬称略)
【モデレータ】 小野 靖 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 教授 |
【登壇者】
 小太刀慶明 経済産業省 イノベーション・環境局国際電気標準課長 |
 財満 英一 (一財)電力中央研究所 名誉研究アドバイザー |
 熊田亜紀子 東京大学 大学院工学系研究科電気系工学専攻 教授 |
 石井 英雄 早稲田大学 スマート社会技術融合研究機構研究院教授 |
 堂﨑 隆志 (一財)電力中央研究所 グリッドイノベーション研究本部 |
 荒牧 隆子 パナソニックオペレーショナルエクセレンス(株)品質・環境本部 |
座談会

当日の様子
テーマ1:標準化活動のプレゼンス
〈小野〉現状の大学や企業内における標準化活動に関する認識は十分かと言いますと,企業では一定の評価を得ている反面,大学はかなり厳しいようです。 まずは現状の企業や大学における標準化活動に関する認識や旅費サポートについておうかがいしたいと思います。
〈堂﨑〉
電中研の場合には,標準化活動に従事している職員もそれなりにおりますので,標準化活動の重要性や必要性は,認識されていると思います。課題は,やはり具体的に誰 がどう従事しているのかが分からないところかと思っています。個人的にはボトムアップでなくトップダウンによって,ある程度標準化活動の評価の仕組みや,重要性というものを改めて周知していただけると,心強いかなと感じています。また,旅費のサポートについては,十分でない場合があり,電気学会の旅費支援事業等に助けてもらっています。 〈熊田〉
大学では,標準化活動に対しての理解はほとんどないのが現状です。大学教員が外部資金の獲得の際に予算の申請書類を書きますが,標準化をアピールする項目がないこ とも現状を表しているかと思っています。また,論文リサーチマップ等でも,“標準化”という単語では検索ができません。
〈財満〉
まずはできることをスタートさせてみて,それを評価していくことが重要かと思います。例えば学会誌や論文誌に国際標準化の特集号を企画することもいいのではないかと思います。 さらに,CIGREではIECの標準化活動に対し,査読もなく掲載されているものがあり,見習うところが多いと思います。まずは,現状の枠組みのなかで動けることはないか検討してみて,進めていくことかと思います。
〈小太刀〉
研究者にとっての最重要事項は研究そのものですので,標準化活動は社会貢献だと位置づけられているのかと思います。標準化活動自体の成果を何らか発表いただけるような場を設けるとか,標準化活動が評価される仕組みを通して,標準化活動がきちっと目に見える形で残るようになりますと,皆さまにとっての意識づけにもなってくるかと思います。また,第一部の講演で若手向けの産業標準化表彰制度を検討していると紹介しましたが,このような表彰の機会を作ることで,標準化への取り組みに手を挙げていただけるきっかけになるかと考えております。さらに,国際会議への出張にも支援体制をなるべく充実させたいと考えています。
〈小野〉
標準化活動が成功するためには,研究活動から標準化へという流れがしっかりできていることが大切で,電気学会では,調査研究をする学会本体と規格役員会の両方の組織を持っています。研究活動から標準化の流れがスムーズに進んだ「需要設備向けスマートグリッド必要化調査専門委員会」についてご紹介いただきたいと思います。
〈石井〉
通称はSGTECです。SGは何の略かというとスマートグリッドです。新しい分野であり,多くの人が関心を持っていたことが大きかったと思います。研究要素も多くありますが,どちらかというといろいろな要素がお互い通信にて結びついて総合力を発揮させていくような分野です。特に通信の領域は,標準化しないとお互いにつなげられない分野であって標準化の意味が非常に強く,活動が盛り上がり,しかも長く続いてきているのだと思います。活動を継続するに当たっては企業の方々を私が所属している大学にて雇用し,専任で活動をしていただきました。つまり SGTEC の活動をコアで支えてきた方々が,専任で活動を推進できたことが非常に大きかったと思っています。メンバーの皆さんにモチベーションをお聞きしたところ,「カーボンニュートラルにとって必要なことだから」や,「これを推進するリーダーシップがあったから」といったご意見をいただきました。
〈小野〉
自分の研究成果が,標準化の合意形成を進めるうえでの技術的な根拠になっているとか,直結した事例はあるでしょうか。そうであれば現状の仕組みのなかでもある程度,標準化に貢献しつつ,大学での評価にも必要な新規性の高い論文が作成できますが,いかがでしょうか。
〈石井〉
直接的に論文になったかというと,あまり実例を挙げることはできないかなと思います。ただ電気学会には,特集記事ですとか,あるいは研究会に論文を多数書いております。これは業績にカウントできるということだと思います。
〈熊田〉
今,石井先生からご自身の研究機構で人を雇用されているとの話がありましたが,それは東大のなかでも徐々には広がりつつありまして,外部資金で週 1 日程度,他の組織とのクロスアポイントメント等が進んできています。専任という訳にはいきませんが,週2 日程度なら何とかなるのではと思います。また,シニアの方で週1日~2日ぐらいなら対応できる方を雇用して,関係する活動を担っていただくことは少しずつ広がってきているかと思っています。
テーマ2:国際標準化における日本のイニシャチブ
〈小野〉では,少し話題も先に進めまして,今度は国際標準化における日本のイニシャチブをどう確立していくかに話を移したいと思います。財満様のご活躍をした TC122での事例をうまく水平展開していき,日本のイニシャチブにつなげていくのがよろしいかと思うのですが,いかがお考えでしょうか。
〈荒牧〉
TC122 での財満様の事例は,王道であると感じます。手本にすべきやり方だなと感じました。その一方で,これをやるには相当なエネルギーが必要とも感じました。交渉では相手からある程度,信頼してもらわない限り,話を進めることができないため,お酒で関係を築いたり相手の国のカルチャーに対してリスペクトするなど,相手が喜ぶポイントを見極めて対応するような変化球も必要かと思っています。
〈堂﨑〉
私がエキスパートを務めております IEC TC57のワーキング13,14では,フロントで活動している日本人は私だけです。そのようななかで感じるのは,荒牧様がおっしゃったことと共通する部分がありまして,自分が提案したときに,相手方からのレスポンスを見て相手と自分の双方にとってメリットがあるような形で進めていく必要があると感じます。また,自分たちと関連するワーキングとうまく連携することで,プレゼンスを上げていくといったやり方もあるのかと最近は思っております。
〈熊田〉
交渉のなかでは人脈作りも重要かと思いますが,学者の場合,人脈作りが苦手な人も多く,どうやって仲間を作っていくは問題かと思います。
〈財満〉
仲間を作っていくうえでは,私は懇親会の場でも決して日本人では集まらず,絶えず外国人のなかに入っていくということを心掛けていました。自らが規格を作ることが大事だと思います。自分で汗をかいてやっていくという意識が非常に大事だと思います。それからもう一つ,できるだけ関係者と協調をとり,なるべく早く標準化委員会とかの場でチームジャパンを作ってやっていくということが大事だと思います。さらに,そのなかでリーダーを1人決めて,各国とのリーダーともうまい関係を作っていくことが,大事かと思います。
〈小太刀〉
これはという分野については,国も合意形成のなかで一歩前に出て役割を果たしていくということがあり得ると思います。チームジャパンという意味では,スピード感もすごく大事だと思っておりまして,しかるべきタイミングで相手に先手を打ち,こちらから提案をすることが大事かと思います。これが逆に先手を打たれてしまうと,跳ね返すことが難しくなりますので,タイムリーに先手を打てるような足の速さをもつ少人数のチームを編成するといったやり方があるかと思います。例えば領域によっては,アカデミアの皆様のなかでこれはというものがあれば,それを国とも議論させていただき,国としてお墨付きを与えるようなやり方も,試行錯誤的にではありますが,物事がスムーズに進むかと思っております。
もう一点,外部人材の活用についてですが,先ほど来,話がされているように,人脈は一朝一夕には築き上げられないものですので,そういったネットワークをすでに持っている方に,いろいろな場でご活躍いただくことが,規格交渉の場でも役に立つと思っています。
テーマ3:分野横断への取り組み
〈小野〉標準化の話は,電気学会だけでは閉じないことが増えてきました。そうすると分野横断的な標準化の動きも,視野に入れて考える必要があるかと思います。そこで分野横断的な標準化に対し,どのような環境整備が必要でしょうか。
〈石井〉
分野横断の傾向が出てきていると思っています。例えば IEC ですでに議論されているのですが,電力システムから電気を使った場合の CO2 の原単位はいくらなのか,定量的に評価をする必要が出てきており,その決め方について,分野横断的な合意が必要ではないかという提案が出されています。また,生成AIの活用なども横断的な取り組みが必要ではないかと思います。
横断的な課題に対しては,私は中核者を決め,その方が中心となって,お互いが連携して国際的に対応していくということが必要なのではないかと思います。私が関わっている SGTECでは国際舞台で,それぞれの分野で個々の対応になってしまっており,横の連携が取れていないと感じます。日本のなかで全体としてどのように対応するのか,どういう連携をするのかを議論する場がもっとあった方がいいのではないかと思います。皆さん,忙しいのでそのような場が持てていません。全体の戦略を常に考えるベテランの人が必要ではないかという気がしています。
〈堂﨑〉
石井先生がおっしゃっているSGTECのなかでは,送配電事業者の協力が十分でないと検討が深まっていかないところがあります。まずは,業界のなかでちゃんとコンセンサスを取っていただくことが必要ではないかと思っております。
テーマ4:オープン&クローズ戦略
〈小野〉競合他社がいるなかで,何をオープンにして何をクローズにするのかは,これは場合によっては国家戦略にもかかわってくるものと思います。次にオープン&クローズ戦略についてテーマを移したいと思います。
〈堂﨑〉
私がかかわっている共通情報モデルという電力技術分野システムのデータモデルに関するところでは,異なるシステムの間でデータ交換するための統一的な方法を提供するといった標準であり,オープン&クローズ戦略に絡めると,クローズになるものは,恐らくアプリケーションプログラムであり,オープンにできるものはそれをどう利用しているかだと思います。バウンダリーをしっかり決めることが必要なのではないかと思います。
〈熊田〉
IEC の関係で規格を策定するための共同研究にかかわった際にメーカの方から「ここから先はクローズにさせてください」ということをはっきりとおっしゃっていて,早い段階でバウンダリーを決めてらっしゃるのだと感じました。会社や大学が持つ強みをさらけだすと,やはり商売のネタをなくしてしまいますので,最初の段階で,お互いコンセンサスを得ておくというのが何よりも大事かなと感じました。
〈小野〉
戦略として,デファクトスタンダードを取りに行く方が良いケースも結構あります。私の専門の核融合分野では多くのベンチャーが最初の核融合炉を作ろうと各国で数千億のお金が動いています。基本的にクローズで,デファクトスタンダードを取ろうとしていますが,国家戦略としてはオープン&クローズ戦略をどのようにお考えでしょうか。
〈小太刀〉
オープン&クローズ戦略というもの自体は,おそらく個社様それぞれの事業戦略のなかで,事業を有利に展開するためにこれをいかに活用するかを考えねばいけない部分と思っております。端的に言えば,事業戦略のなかで儲けになる部分はクローズにして,競合他社と差別化をする。一方で市場のパイ全体を広げるためにはオープンにしていく部分も大事です。やはり,このツールを使いながら,全体のパイを広げつつ,クローズで差別化を図り,シェアを取り儲けていくという使い分けをするのがオープン&クローズ戦略だと認識しています。そういった戦略をどうやったらうまく使えるかという方法論について,国としても各社様のエッセンスを共有,発信できれば日本の産業競争力全体を高めることにもつながっていくと考えています。
それから,有効な戦略を立てるためには,正しい判断をするためのベースとなる情報をいかに集めていくかも非常に大事だと思っております。そのような情報インテリジェンス機能について,プラットフォーム的な部分も,国として整備できることもあるかと思っております。
さらに,もう一点だけ申し上げますと,オープンに協調して進めていく部分は,仲間作りが大切になってまいります。協調領域の合意形成では,国としても力になれる部分があると思っております。
テーマ5:人材育成・後継者育成
〈小野〉それでは次に,人材育成・後継者育成のテーマに進みたいと思います。標準化の分野では年齢層が高いという話は何度も出てきていますが,シニア人材を活用したらどうかというような話もあります。そのようななかで,まず,若手として標準化活動にかかわられた堂﨑様のご経験を皮切りに人材育成について考えてみたいと思います。
〈堂﨑〉
私は30歳の時に,初めて標準化活動に携わり始めました。最初の2年間は何も提案できるものがありませんでした。ワーキングに参加しているエキスパートの方に同行して,国際標準の動向やそこに出席している各国のエキスパートの方の人柄や,立場とか,加えてどのような関心事項でワーキングに参加しているのかといったことを,2年間,作業会のなかで学びました。2021年になって自分の研究に進捗があり,初めてワーキングのなかで標準化の提案を行い,そして,現在に至っています。
〈石井〉
私が行っている人材育成に関する取り組みをご紹介しますと,卓越大学院という文部科学省の仕組みのなかで,博士課程の学生に必修科目を作っています。そのなかに国際標準化という科目を入れました。国際標準化の授業を受けてもらい,テストも受けてもらうような仕組みでして,演習もやってもらっています。この仕組みのなかで,EMS(エネルギーマネジメントシステム)でさまざまな機器をコントロールする際に,”標準”があるとどれだけ簡単にプログラミングができるかを経験してもらっています。講義の部分では,標準化とは何か,標準がなかったらどうなるのかからスタートしており,日本規格協会の出されている資料などを活用しています。
また,日本規格協会が標準化の事例を出されていて,これは私も勉強になりましたし,学生も非常に強い衝撃を持って受け止めてくれています。関心を持ってもらうことが大事だと思います。やはり学生の時分からそのような知識を持ってもらうことが,育成ということでは重要なのではないかなと思います。
また,実際に TC8 に若い人を連れていき,入口のところを経験してもらうこともやってまいりました。そういうことで先ほど財満様からもありましたけれど,先導する人が意識して後輩を育てる,これが本当に必要なのではないかと思います。
〈荒牧〉
私も大分若手を育ててきましたが,一方で,育ったら転職してしまうというケースも結構経験しました。そのような時には一企業ではなく日本全体という立ち位置で見れば,自分も貢献しているのではないかと思うようにしています。転職してしまった場合には代わりの若手を育てなければならず,重複にはなりますが,人が育つことは非常にいいことだと思っています。
〈熊田〉
石井先生が科目を作られたことは素晴らしいなと思ってお聞きしておりました。持ち帰って研究科の会議で提言しようと,決心しました。電気だけでなく,工学全体で社会課題の解決と,社会実装が今は大事なキーワードになっていますので,社会実装していくうえでは標準化のルールを知らないと話にならないことから,工学系の共通科目に入れられないか,ロビー活動を始めたいと思いました。
学生の育成は,授業内で行うことになるかと思います。研究者には標準化活動よりは研究をやっていただきたいので,そこは学会活動などで,雰囲気を味わっていただくのがよいかと思います。例えば,若手の先生は電気学会で調査専門委員会の幹事などをやっていらっしゃいますので,そういう場に関連する標準規格などのトピックを取り上げることが考えられます。標準化のエキスパートの方をお呼びし,講演をしてもらい,自分の専門分野との関わりがもてると,その後の活動にも士気が上がるかと思っています。また,シニアの方にご活躍いただくこともいいかと思います。
〈財満〉
先ほどの石井先生の話は非常に含蓄があって,授業課題に取り入れていただいているということは素晴らしいことだと私も思います。大学では国際標準化への素養を作ってもらいたいと思います。国際標準化にかかわるのは,企業に入ってからが多いと思います。企業に入ってからできるだけ早くに誰かにくっついて会議に出席するような経験をさせて,勉強させることも大事だと思います。石井先生が大学のなかで取り組まれていることは,正に石井先生が司令塔となってチームジャパンの活動をやっていただいており,期待しているところです。大学の先生方のなかに,そういう司令塔級の方を作っていただき,そこに経産省からのお墨付きと資金をもらうことができれば先生方の実績としても評価されます。また,なるべくそのような場に学生を引っ張り込んで経験させれば,役に立つのではないかと思います。
〈小野〉
人材をうまく活用する施策として,経産省が中心になってリードしていただいた,STANDirectoryがあります。こちらについて,どのようにお考えでしょうか。
〈荒牧〉
副業という課題があるかと思います。また,弊社の場合独自のデータベースを持っています。一方で,弊社は,社内外での副業を解禁している部署もありまして,他社も含めて制度も変わりつつあると感じますので,そろそろSTANDirectoryのようなものも活用できるのではと思います。一方でマインドの面ではなかなか難しいケースもあるかと思っています。何かしら自己実現に結びつける形でうまくインセンティブを与えることができればこういう仕組みが機能するかと思います。
〈堂﨑〉 まず前提として事業者である企業だとか,業界団体の方が,データベースの存在を知っていただくことが重要だと思います。そのために,引き続き周知が必要であると思います。また,実際に活用する際に,このデータベースの登録情報に基づいてその利用者である企業や業界団体の方が該当する標準化人材の属する組織にコンタクトをするのだと思いますが,好事例や実績の紹介があるとよいかと思います。
〈石井〉
私自身あまり存在を認識していなかったのが正直なところです。これを使う側は,相談とかアドバイスだとか,あるいは仲間を作るということかと思いますが,登録する側の人のメリットがあるのかが頭に浮かびました。活用事例のアピールが必要なのかと思います。
〈小太刀〉
本日の論点としてSTANDirectoryを取り上げてくださったことにお礼を申し上げます。昨年の 6 月にリリースしたばかりで具体的にどのような形で使われているのかについては,フォローしきれていない部分もございます。あくまでも,人材情報を提供するところまでで,そこから先で何かが成約したとか,そういう仲介までをやっているわけではございません。いろいろな方からお話をうかがって活用例を収集しており,そのなかからベストプラクティスをご紹介し,使い方もさらに充実させたいと考えているところです。そのなかで,社内研修の講師を探しているときにご活用いただいたというようなことは聞いており,そういった事例を,随時お知らせできればと思います。
また登録する側のメリットですが,お名前が登録されていること自体が何らかのアピールになりうるという姿を見せたいと思います。標準化の分野でのサポートを展開されたいという方におかれまして,PRになるかもしれません。そのような点を含めて,ヒアリング等々,進めたいと思います。
〈小野〉
ありがとうございました。活発にご議論いただいているうちに,ほぼ時間を使い切りました。日本型の標準加速化モデルをスタートに,内外の問題を考え,こんな対策があるのかと気づくいくつかの重要なご示唆をいただきました。電気学会としても,あるいは電気規格調査会といたしましても,ご指摘を踏まえて,これからいかに標準化活動を支えていくか,さらに,広げていくか考えていきたいと思います。ご参加の企業,それから大学それから経産省におかれましてもこれから継続的にこうした問題を考え,知恵を絞っていただければと思います。
今日はパネラーの皆様と議論ができまして本当に有益でした。改めて御礼申し上げます。会場の皆さまも雪のなか,ご清聴いただきまして本当にありがとうございました。これにてシンポジウムを終わらせていただきます。