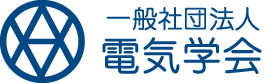活躍する女性エンジニアたち、電気系職場の今を語る(第2回)

座談会参加者
-
東芝インフラシステムズ株式会社
水谷 麻美さん
みずたに まみインフラシステム技術開発センター
技監
博士(工学) -
東日本旅客鉄道株式会社
中島 志穂さん
なかじま しほ東京電気システム開発工事事務所 品川電気システム工事区
電車線科 -
株式会社安川電機
三松 沙織さん
みまつ さおり技術開発本部
つくば研究所 先端技術グループ
司会
-
東海大学
稲森 真美子さん
いなもり まみこ工学部
電気電子工学科
准教授
博士(工学)

自分が苦労して作ったモノが完成し、使ってもらえる喜び
— 稲森:みなさんは、今、就いているお仕事でどのような点にやりがいを感じていますか。
中島:私は、多くの人が利用するモノを作ることに、とてもやりがいを感じています。2020年には、とても大きな仕事がありました。品川駅の切換工事と高輪ゲートウェイ駅の開業です。このように世間的にも話題性があり、多くの人の関心を集めることの一部に自分が関わっていることが、とても楽しく、誇らしく感じました。一緒に働く、若い人たちも同じような思いを持ったのではないでしょうか。
水谷:私も製品に近い部署にいます。苦労して作り上げたモノが実際に出来上がって、納品され、現場で動いたときの達成感は他では味わえないものです。電力向けや鉄道向けなど、様々な蓄電池製品を扱っているのですが、電力会社向けに大きな蓄電池システムを納入し、見渡す限りの敷地に作った製品のコンテナが並んだ様子を見た時には、本当に感無量でした。これは、メーカに入社してよかったなと思う瞬間です。また、開発している過程でも、鉄道会社などお客様と話す機会が多くあり、こうしたやり取りも、気づきや課題が見つかるので面白いと思います。
三松:私は研究所にいるので、製品開発に直接関わっているわけではありません。ただ、自分の仕事を喜んで使ってくれる人がいると嬉しく感じます。まだ、大きなシステムを完成させるような経験をしたことはないのですが、既存のシステムで抱えていたトラブルを、原因を探求して解決したりするなかでやりがいを感じています。
— 稲森:中島さんは、大学時代には送電設備に影響する自然現象に関する研究をされていたと思いました。現在携わっている工事でもその知識は生かされるのではないかと思うのですが、大学時代の延長線上の研究をしてみたいとは思わなかったのですか。
中島:大きなくくりでは、関連していますが、今の仕事では大学でやっていた研究のテーマに関連したことにはまったく関わっていない状態です。むしろ、大学時代に碍子を使った研究をしていたと言うと研究部門に配属されそうだったので、会社に入ってからは口にしないようにして過ごしてきたくらいです。研究はやりたくなかったのです。
— 稲森:なぜですか。
中島:大学の4年生と大学院で毎日のように研究したので、もういいかなと思ったのです。研究所に入って、コツコツと研究するのに、孤独で暗いイメージを持っていたのです。本当に勝手なイメージなのですが。
三松:今では、企業の研究所も意外と自由ですよ。事業部では、常にお客様に合わせて動く必要がありますが、研究所では自分で仕事を管理する時間的余裕があるように感じています。特に、私が所属するつくば研究所では、セレンディピティ(偶然の出会いや予想外の発見)を大事にしており、いろいろな所に行って、様々な話を聞いて、刺激を受けて、良い研究をしてほしいという運営がされています。安川電機の中では、特に自由で特殊な部署かもしれません。私も、研究に直結すること以外の活動にも参加して、結構楽しく過ごしています。