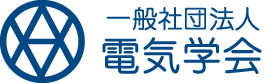活躍する女性エンジニアたち、電気系職場の今を語る(第3回)-2ページ目


女性エンジニアの先駆者が後輩を育て環境を整える時代に入った
— 稲森:みなさんは、これからのキャリアをどのように考えていますか。
水谷:私は、会社員としては、先があまり長くないので、若い人が思うように仕事ができる環境を整えていくことができればと思っています。昔の自分もそうだったのだと思いますが、まだまだ人材のポテンシャルを引き出すための方策はいろいろあるのではと考えています。もっとも、一番伸びしろがあるのは日本語力かもしれません。考えていることを誰かに伝えることができないと、大きな仕事はできませんし、そもそも何を考えているかすらわかりません。そんな文を書く人が多いように思えますから、そこはキッチリと正していきたいです。
三松:私は、つくば研究所に来てから、よりジェネラリストに近い技術者を目指したいと考えるようになりました。そしてもっと多くの分野と、メカトロニクスとの接点を作っていきたいと考えています。社内には、様々な分野のスペシャリストが何人もいます。私は、いろいろなものに興味を持ち、新しいことが好きなので、あちこちにアンテナを張って、社内や社外のプロフェッショナルと一緒に新しいことができる仕事ができればいいなと思っています。
また、学会やコンソーシアムなどに参加し、先生方や各方面の専門家の方々からヒントをもらって、仕事の問題を解決するのがとても楽しいので、そういう環境づくりも社内の中で進められればと思っています。私が所属する安川電機は、本社が九州にあり、つくば研究所は関東の出島のような位置付けで、社外と関係しやすい反面、社内の人とは疎遠になりがちです。もっと社内外両方の人とつながりを深めながら仕事をしていきたいと思っています。
中島:私は、今は夜中に働く仕事なのですが、現場では、私よりもずっと年上の作業員が夜中に高い場所に登って電線を張るような作業をしています。危険で、きつい仕事です。こうした仕事のやり方を変えたり、そもそも電車線という設備を不要にするような技術を生み出したりする技術者になっていきたいと思います。それが実現すれば、今の私の仕事もなくなってしまうことにはなるのですが。また、管理者としての立場からは、後輩を育てたり、悩みを聞いたりするのが私の役割かと思います。
今までにも増して電気が重要な時代が到来、女性の力が欠かせない
— 稲森:最後に、これから電気工学を志す人、電気系の企業への就職を考える人にメッセージをお聞かせ下さい。
三松:就職するまで、電気工学は、小中高の授業の中で学んだ理科の中の一分野というイメージにすぎませんでした。しかし、実際に自分が関わってみると、世界のいたるところで電気工学の成果が使われていて、いろいろな分野との接点がある学問であることに気が付きます。いろいろなことに興味を持つ人に入ってきてもらえたらなと思います。
中島:私は、大学でも電気工学を専攻したのですが、足を踏み入れたのは大学入試の日程の関係でたまたま合格したからという偶然からでした。そんな私も、入ったからには10年間はこの分野でがんばってみようと考え、大学での研究、企業での仕事を続けてきました。その結果、私自身びっくりするほど、のめり込める面白さを味わうことができています。ぜひ、この分野に入って、続けてみて下さい。きっと、面白さを実感できると思います。
水谷:自動車の分野でも、ガソリン車がなくなり、電気自動車に替わっていく時代になりました。これからは、電気の時代で、世の中のすべてが電気で動く社会になります。電気工学の重要性はますます高まり、勉強する価値と意義がある学問だと思います。私は、学位を取ったといった、高い専門性を持っているかのような話をしましたが、実は交流の計算が苦手でいまだに分かっていないところがあります。幸い専門の電池は直流なので助かっていますが、オームの法則さえわかっていればやっていける世界もあります。このように電気工学は多様で、きっと得意な専門が見つかると思います。怖がることなく、ぜひ挑戦してみることをお勧めします。
— 稲森:女性エンジニアの会には学生も参加しています。社会のことを知らない学生は、男性社会の中で女性が生きるためには、男性を圧倒するようなすごい能力を持った人にならなければいけないのではないのではという気負いがあるようなのです。それが女性エンジニアの会に参加して、先輩たちの等身大の話を聞くと、安心するみたいです。すごい人ばかりではなく、みんな必死でもがきながら仕事をしていることを肌で感じるからです。みなさんのお話を聞いて、臆することなくメーカに就職し、精一杯活躍してもらえるとうれしいです。本日は、どうもありがとうございました。
関連イベントのご案内
「女性エンジニアの会」は、産業応用部門大会の会期中に併設されています。キャリアに関する講演や座談会形式でのフランクな意見交換の機会,夜は有志による懇親会も開催され,様々な交流の場を持つことができます。詳細は,各産業応用部門大会のホームページにご案内があります。